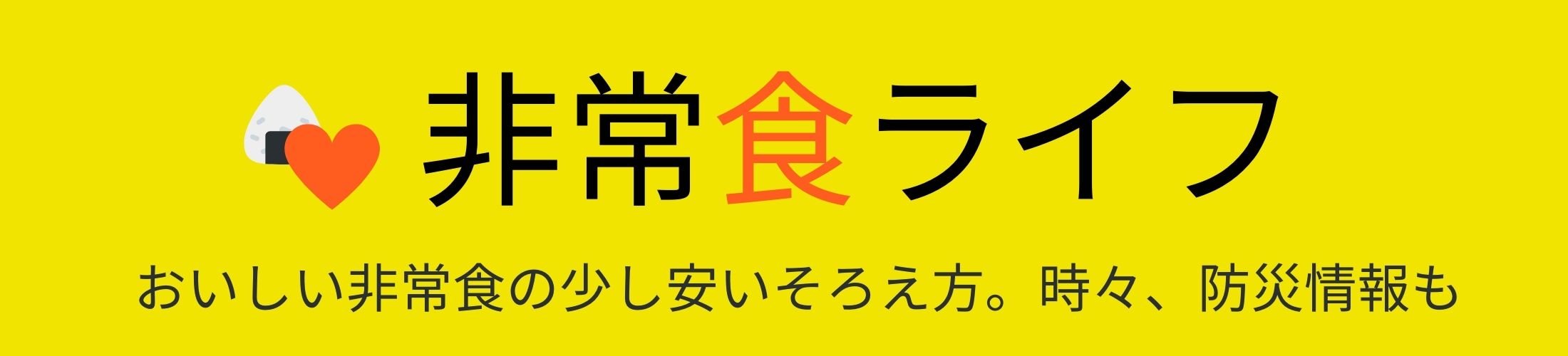9月1日の防災の日を中心に、備蓄や非常食についての話題が増えてきました。そんな中、全国的に関心が高まっているというデータが発表されました。
備蓄経験ありは7割
9月21日の日経MJより。
花王生活者研究センターがまとめた家庭の備蓄に関する調査で、非常食の備蓄に関する関心が高まっていることがわかりました。
この調査は6月から7月にかけてインターネットのサイトで約1万6000人に調べたもの。
「備蓄をしたことない」という人は、26%。去年の同じ時期よりも11ポイント少なくなったそうです。実に7割以上が、「備蓄したことがある」「備蓄している」と答えたということになります。
「1週間以上備蓄」は16%
では、何日くらい備蓄するかというと、3日分という人が一番多くて4割近くだそうですが、4~6日や1週間以上という人も10%以上いました。

かなり関心が高まっていますね
災害増加もですがコロナも原因か
この数年、毎年のように多くの方が亡くなる災害が全国的に起きています。
地震によってインフラ・物流が寸断され、食事に困る場合
水害で断水、停電
台風で断水し、タワーマンションで水を手作業で運ぶ
こうした場面を目にすることが本当に増えました。やはり備蓄しようという雰囲気にはなるのでしょう。
それに加えて、新型コロナウイルスによる影響もありそうです。
長時間、家にいることから、より長期間の備蓄が必要と感じるようになったり、社会的なインフラ・物流への仕組みへの不安感なんてものもありそうです。畑を借りて、自給自足を目指す人が急に増えてきたような話も聞きます。自らの身を守ることの一環としての備蓄とも言えるのではないでしょうか。
まとめ
ちなみに備蓄するものとしては、水・ミネラルウォーター、レトルト食品、みそ汁、缶詰など。いわゆる食料の備蓄ですね。他にもトイレットペーパー、マスク、除菌スプレーなどもあり、やはりコロナ時代の備蓄への考え方の変化を感じさせるものとなりました。
多めに食材を置いておいて、古いものから順番に使う「ローリングストック」が、やはりおススメです。
 我が家のローリングストックリスト!注意点は?コツは「いつもの食材を気楽に備蓄」
我が家のローリングストックリスト!注意点は?コツは「いつもの食材を気楽に備蓄」  「ローリングストック」のススメ 「非常食を1週間分備蓄」って無理なので
「ローリングストック」のススメ 「非常食を1週間分備蓄」って無理なので