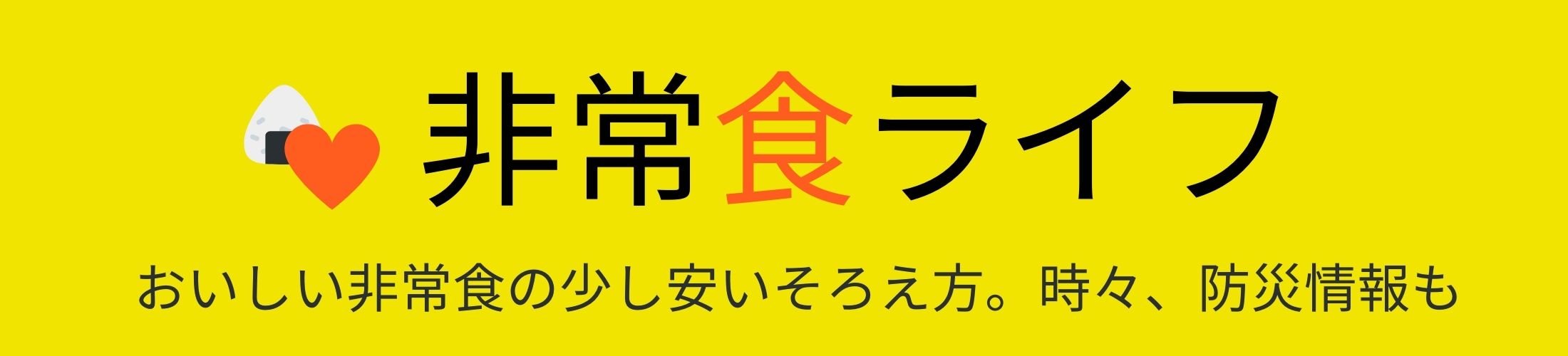災害後の3つの段階
災害後といっても、大きくわけると3つの段階にわけられます。
まずは「災害直後の3日間」。身の安全をはかり、安全な場所に避難する時期です。地震ならば火事も起きているかもしれません。消火活動が続く中、延焼の不安のない場所へ移動することも必要です。(避難所で過ごすことは意外と多いということは別記事でも書いています→「避難所で過ごす可能性って、自分で思っているより多いというお話」)
次に「1週間までの間」。地震ならば余震が落ち着いて、家が破損していなければ自宅に戻れる時期です。水害などでも、道が整備され、多くの人が浸かってしまった家に戻ることができるようになります。それでも家の食料を持ち運んで避難所で過ごすことになるかもしれません。
そして「1ヶ月までの間」。電気が回復し、炊飯器やポットが使えます。食材は不足していますが、ある程度、被災者向けの食材がまわってきます。
「避難所に持って行く非常食」
「避難所に持って行く非常食」というのは「非常持ち出し袋に入れておく非常食」と、ほぼ同じです。
注意点としては・・・
子供用のミルク、アレルギーなどの体質に合わせた対応食などが必要な人は、必ず持ち出し袋に入れておきましょう。避難所で、アレルギーのない非常食がもらえるとは限りません。
マイ防災セットを作っておきましょう。すぐに食べられる缶詰パンやレトルト食品などのほか、お菓子など、自分が食べたいものを入れておくのがベターです。
市販の防災セットはあまりおすすめしていない(自分で作る方が良いため)のですが、ひとつ選ぶならコレという記事は書いています→防災セットをひとつオススメするなら「ラピタ」の「ものすごい防災セット」を選びます
「家に置いておく非常食」
一方で、家に置いておいてもよい非常食というと、発災から数日たってから家に帰って、家で食べるものや、避難所へ持って行くものを想定しています。アルファ米や、かさばる缶詰やレトルト食品などですね。アルファ米については、かなり細かく書いています→「アルファ米のおすすめをまとめました(実食レビューつき)」
もちろん保存水も、これにあたります。水は大人1人で1日3リットル必要と言われています。最近は10年保存水というものもでているので、しっかりと備蓄しておきたいですね。
災害は長く続きます。発災当初の「簡易的な非常食」だけで過ごすと、あっという間に体調を崩すことになり、高齢者や子供の場合は命の危険につながる可能性すらあります。しっかりと栄養に気を使った食材を備蓄したいですね。
特に気にしたいのは野菜などビタミン・ミネラルの豊富な食材です→「非常食の野菜不足にカゴメ野菜の保存食を全力でおすすめ」
ビタミン剤などの栄養補助食品も、あればこしたことはありません。(非常食が続くとかなりの確率で口内炎になりますので…ビタミンBの錠剤などでしょうか)
ちなみに、この時期にマストなものが「カセットコンロ」です。アルファ米やレトルト食品があれば、暖かいご飯を食べることができます。このブログでもかなり強力におすすめをしています→「カセットコンロって防災セットに入っていないけど必需品」
まとめ
非常食について調べて、実食レビューを書いていると、いま市販されている「防災セット」がいかに不十分かを感じることが多くあります。防災セットに文句を言おうというワケではなくて、防災セットに入っている非常食って、発災直後に元気が出るものがメインなんですよね。
でも実際には、被災生活ってすごく長く続くので、そうした長い被災生活に役に立つ備蓄をおすすめできたらいいなと思っています。→「非常食の揃え方をわかりやすく解説!どこで・何を・どう揃える?」
普通に暮らしていて、大災害にあうことは人生にそこまで多くはありません。となると、想像して、何が必要か考えて、それを備えるということが大事になってきます。
このブログが、そのきっかけのひとつとなれば嬉しいなと思います。